
「大義」と「大儀」は、同じ「たいぎ」と読むものの、意味がまったく異なります。
「大義名分」という言葉はよく聞くけれど、「大儀である」との違いが分からない…そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
実は、「大義」は正義や大きな目的を意味し、「大儀」は面倒くさい、億劫といった意味を持つ言葉です。
本記事では、それぞれの違いを一覧表で分かりやすく比較し、正しい使い方や誤用しないためのポイントを詳しく解説します。
「大義」と「大儀」の違いをしっかり理解し、適切に使い分けられるようになりましょう!
ぜひ、最後までご覧ください。
「大義」と「大儀」の違いを一覧表で確認!
まずは、「大義」と「大儀」の違いを分かりやすく表にまとめました。
| 大義 | 大儀 | |
|---|---|---|
| 意味 | 正当な理由、大きな目的・使命 | 面倒くさい、億劫・ご苦労(ねぎらいの言葉) |
| 使われる場面 | 政治、戦争、ビジネス、道徳 | 日常会話(古風)、時代劇、歴史小説 |
| 例文 | 「国家の大義のために戦う」 「彼は人としての大義を貫いた」 |
「歩くのも大儀になってきた」 「武士が家臣に『大儀である』と言う」 |
| 関連語 | 大義名分(正当な理由) 義を見てせざるは勇無きなり(道義を果たさないのは勇気がない) |
大儀そうな顔(面倒くさそうな表情) 大儀をねぎらう(苦労をねぎらう) |
「大義」は道徳的な正しさや正当性のある目的を示すのに対し、「大儀」は主に「面倒くさい」という意味や、目上の人が目下の人を労う言葉として使われるのが特徴です。
「大義」と「大儀」の違いを詳しく解説!
それでは、「大義」と「大儀」の違いをより詳しく説明していきます。
「大義」は、歴史や政治、ビジネスの場面でよく使われる言葉で、「正当性」や「大きな目的」を示すときに使われます。
例えば、戦争や革命の理由として「大義」が掲げられることが多く、歴史上のリーダーたちも「大義」を大切にしてきました。
「大義名分」という言葉は、まさにその正当な理由を示すものです。
一方で、「大儀」は日常生活や古風な表現として使われる言葉です。
「面倒くさい」「億劫だ」という意味で使われることが多く、特に高齢者が「最近、歩くのも大儀になってきた」などと言うことがあります。
また、時代劇などで「大儀である」というフレーズを聞いたことがある人も多いでしょう。
これは、目上の人が目下の人に対して「ご苦労であった」とねぎらう言葉として使われます。
このように、「大義」と「大儀」は同じ「たいぎ」という読み方ですが、意味がまったく異なります。
誤用しないように、それぞれの意味をしっかり理解しておきましょう。
「大義」の意味と使い方
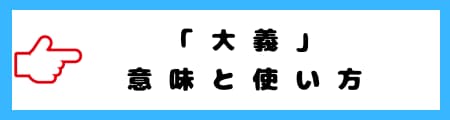
「大義」は「正義」や「大きな目的」を表す言葉
「大義(たいぎ)」は、正当な理由や大きな目的を表す言葉です。
「義」という漢字には「正しい道理」や「倫理的な正しさ」の意味があり、それに「大」がつくことで「より大きな正しさ」「社会的に重要な使命」を意味します。
歴史的に見ると、「大義」は戦争や政治の場で特に重視されてきました。
戦国時代の武将や幕末の志士たちは、「国のため」「民のため」といった大義を掲げ、それを理由に戦いを起こしたり、政策を推し進めたりしました。
また、現代においても「大義」は使われており、政治家や企業家が「正当な目的」を強調する際によく用いられます。
例えば、「大義を持つ政治家」と言うと、「社会のために正しい目的を持って行動する政治家」という意味になります。
「大義がない行動」と言えば、「正当な理由がなく、道義に反する行動」を指します。
このように、「大義」は非常に道徳的な意味を持つ言葉です。
政治や戦争での「大義」の使われ方
「大義」は、特に政治や戦争において重要な概念として扱われます。
歴史的に見ても、「大義」が戦争や革命の正当性を示すために用いられてきました。
例えば、戦国時代の武将たちは「天下統一」という大義を掲げて戦いました。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった歴史上の人物たちは、それぞれの大義のもとで行動し、時には戦いを起こしながらも、最終的には日本を統一することに成功しました。
また、幕末の志士たちは「尊王攘夷(そんのうじょうい)」という大義のもとで行動し、明治維新を成し遂げました。
このように、戦争や政治において「大義」を持つことは、その行動の正当性を示すために非常に重要でした。
現代においても、国際政治の場では「大義」が重視されることが多く、例えば「この戦争には大義があるのか?」という問いかけがなされることがあります。
例文:
- 「この戦争には大義があるのか?」(=正当な理由があるのか?)
- 「リーダーには大義を持った決断が求められる」
- 「彼は国のために戦うという大義を掲げた」
日常会話やビジネスでの「大義」
「大義」は、戦争や政治だけでなく、日常会話やビジネスの場でも使われることがあります。
例えば、ビジネスの世界では「企業の社会的責任(CSR)」が重要視されていますが、これはある意味で「企業の大義」と言えます。
単なる利益追求ではなく、社会に貢献することを目的とする企業は、「大義を持った企業」として評価されることがあります。
また、日常会話においても、「彼の行動には大義がある」といった表現が使われることがあります。
これは、「彼の行動には正当な理由や高い目的がある」という意味になります。
例えば、ボランティア活動や環境保護活動をしている人に対して、「彼の行動には大義があるね」と言うことができます。
例文:
- 「利益だけでなく、社会的な大義も考えるべきだ」
- 「彼の行動には大義が感じられる」
- 「このプロジェクトには大義があるのか?」(=社会的に意味のある目的があるのか?)
「大義名分」の具体的な意味と例文
「大義名分(たいぎめいぶん)」という言葉は、「行動の正当な理由や根拠」を意味する四字熟語です。
特に政治やビジネスの場面でよく使われます。
「名分」とは「筋が通った理由」のことであり、「大義名分」とは「大きな正義に基づいた理由」を指します。
例えば、何か大きな決断をするときには、「大義名分」が必要とされます。
企業が大きな改革を行うとき、政治家が政策を打ち出すとき、戦争を始めるときなど、すべてにおいて「大義名分」が問われるのです。
もし大義名分がなければ、その行動は正当なものとして認められず、批判を受けることになります。
例文:
- 「改革には大義名分が必要だ」
- 「彼は大義名分を掲げて会社を立ち上げた」
- 「戦争をするには、まず大義名分を明確にしなければならない」
「大義」が使われることわざや慣用表現
「大義」は、いくつかのことわざや慣用表現にも使われています。
例:
- 「大義を貫く」(正しい道理を守る)
- 「大義の前に私情を捨てる」(正しいことを優先し、自分の感情を抑える)
- 「義を見てせざるは勇無きなり」(正しいことを知りながら行動しないのは、勇気がない証拠)
このように、「大義」は道徳的な正しさや正当性を示す言葉として、現代でも重要な役割を果たしています。
まとめ:「大義」は正当な目的や使命を示す言葉
「大義」とは、道徳的な正しさや社会的に大きな目的を示す言葉です。
特に政治や戦争、ビジネスの場面でよく使われ、「大義名分」という言葉も広く知られています。
- 「大義」とは、正義や社会的に重要な目的を示す言葉
- 政治や戦争、ビジネスの場でよく使われる
- 「大義名分」は、正当な理由を示す言葉
これらのポイントを押さえて、「大義」を正しく使いこなしましょう!
「大儀」の意味と使い方
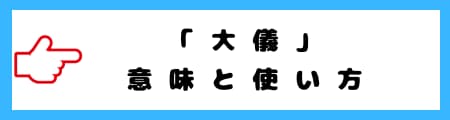
「大儀」は「面倒くさい」や「億劫」という意味
「大儀(たいぎ)」は、「面倒くさい」「億劫である」「身体的にしんどい」という意味を持つ言葉です。
現代ではあまり一般的に使われることは少なくなりましたが、特に高齢の方が「最近は何をするにも大儀になった」などと使うことがあります。
また、「大儀」は、時代劇や歴史小説などの古風な表現としてもよく登場します。
例えば、体調がすぐれずに動くのがしんどいとき、「起きるのも大儀だ」と言うことができます。
この言葉は、古くは武士の世界でも使われており、「戦の疲れで大儀だ」といった表現が見られました。
つまり、「大儀」という言葉には、「疲れや加齢などによって、行動するのがつらい」というニュアンスが含まれているのです。
例文:
- 「朝起きるのも大儀になってきた」
- 「疲れていて歩くのも大儀だ」
- 「彼は大儀そうな顔をしていた」
このように、「大儀」は「身体的・精神的に面倒くさい、つらい」という意味で使われることが多いです。
時代劇でよく聞く「大儀である」の意味
「大儀」という言葉を耳にする場面として最も多いのは、時代劇ではないでしょうか。
時代劇では、武将や殿様が家臣に向かって「大儀である」と言うシーンがよくあります。
この場合の「大儀である」は、「ご苦労であった」「よくやった」という意味になります。
これは、昔の武士社会において、上司が部下をねぎらう際に使われていた表現です。
「お疲れ様」と言うよりも格式があり、上から目線の言葉なので、現代では使われませんが、歴史ドラマや小説などでしばしば見られます。
例文:
- 「戦い、ご苦労であった。大儀である」
- 「遠路はるばる参ったな。大儀であった」
- 「そなたの働き、誠に見事であった。大儀である」
つまり、「大儀である」は、目上の者が目下の者に向かってかけるねぎらいの言葉です。
現代の会社で上司が部下に「大儀である」と言うと、かなり違和感があるので注意しましょう。
「大儀」は現代ではあまり使われない?
「大儀」という言葉は、現代では日常会話で使われることはほとんどなくなっています。
特に若い世代では聞く機会が少なく、時代劇や歴史小説でしか見ない言葉になりつつあります。
しかし、高齢者の間ではまだ使われることがあり、例えば祖父母世代の人が「年を取ると、何をするにも大儀になってくる」と言うことがあります。
この場合、「億劫になってくる」「面倒に感じる」という意味になります。
また、伝統的な会社や格式のある場では、「大儀」という言葉が使われることがありますが、これは主に儀礼的な場面でのねぎらいの表現としてです。
現代での使われ方の例:
- 年配の人が使う:「最近、歩くのも大儀だなあ」(=しんどい、億劫だ)
- 伝統的な会社で使う:「この度の働き、大儀であった」(=ご苦労であった)
- 時代劇で使う:「よく戦った、大儀である!」(=労いの言葉)
このように、「大儀」は古風な言葉として今も一部で使われていますが、一般的な日常会話ではほとんど使われなくなっています。
歴史の中での「大儀」の使われ方
「大儀」は、特に江戸時代の武士の間でよく使われていました。
戦国時代や江戸時代の武将たちは、家臣の働きをねぎらうために「大儀である」と言ったり、戦に出る際に「これは大儀なことだ」とつぶやいたりすることがありました。
また、江戸時代の庶民の間でも、「大儀」という言葉は使われていました。
「大儀じゃのう」と言えば、「面倒くさいなあ」という意味になり、年配の人が若者に「わしも昔は元気じゃったが、今ではすっかり大儀でのう」と言うような場面もあったようです。
歴史上の使用例:
- 「戦に出るのも、そろそろ大儀になってきた」
- 「そなたの忠義、見事であった。大儀である」
- 「この年になると、何をするにも大儀じゃ」
現在ではほぼ時代劇や歴史小説の中でしか使われませんが、かつては日常的に使われていた言葉なのです。
「大儀」と似た意味の言葉
「大儀」と似た意味を持つ言葉として、以下のようなものがあります。
| 言葉 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 億劫(おっくう) | やる気が出ず、面倒に感じること | 「朝起きるのが億劫だ」 |
| 面倒(めんどう) | 煩わしい、手間がかかる | 「手続きが面倒くさい」 |
| しんどい | 体が疲れていてつらい | 「仕事がしんどい」 |
特に「億劫」は「大儀」と意味が近いため、現代では「大儀」の代わりに「億劫」が使われることが多いです。
まとめ:「大儀」は「面倒くさい」「ねぎらい」の言葉
「大儀」は、「面倒くさい」「しんどい」という意味で使われる言葉で、現代ではあまり使われなくなっています。
しかし、時代劇では「大儀である」という形で「ご苦労であった」という意味でも使われます。
- 「大儀」は「面倒くさい」「億劫」の意味
- 時代劇や歴史小説でよく使われる
- 「大儀である」は目上の人が目下の人をねぎらう言葉
このように、「大儀」は現代では使われる場面が限られているため、誤用しないように注意しましょう!
「大義」と「大儀」を間違えないためのポイント
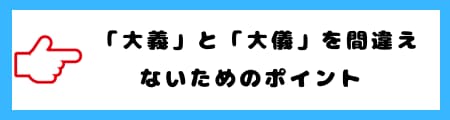
「大義」と「大儀」は、同じ「たいぎ」と読むため混同されやすいですが、それぞれ意味が大きく異なります。
間違えて使ってしまうと、文脈によっては意味が通じなかったり、誤解を招いたりすることがあります。
ここでは、「大義」と「大儀」を正しく使い分けるためのポイントを詳しく解説していきます。
意味をしっかり理解するコツ
まず、「大義」と「大儀」の基本的な意味を明確に押さえましょう。
| 大義 | 大儀 | |
|---|---|---|
| 意味 | 正義・正当な目的 | 面倒くさい・億劫 |
| 使われる場面 | 政治、戦争、ビジネス、道徳 | 日常会話(古風)、時代劇 |
| よく使われる表現 | 「大義名分」「大義を貫く」 | 「大儀である」「大儀そうな顔」 |
| 例文 | 「彼は国のための大義を掲げた」 | 「彼は歩くのも大儀になってきた」 |
このように、「大義」は社会的な正義や目的を示し、「大儀」は個人的な感覚で「面倒くさい」「しんどい」という意味を持ちます。
特に、「大儀である」という表現は、時代劇などで目上の人が目下の人を労うときに使われるため、「大義」と混同しないよう注意が必要です。
文章の中での自然な使い方
「大義」と「大儀」を誤用しないためには、文章の文脈に注意することが大切です。
以下の例文を見比べてみましょう。
誤用例:
❌ 「この仕事には大儀がある」 → 「大義」が正しい(仕事には正当な理由が必要だから)
❌ 「戦争には大儀名分が必要だ」 → 「大義名分」が正しい(戦争の正当性を示す言葉だから)
❌ 「最近、何をするのも大義だ」 → 「大儀」が正しい(面倒くさいという意味なら「大儀」)
このように、文章の中で適切な意味を考えながら「大義」と「大儀」を使い分けることが重要です。
誤用しやすいケースを紹介
「大義」と「大儀」を間違えやすい場面をいくつか紹介します。
-
スピーチや文章での誤用
- 「私たちのプロジェクトには大儀がある」→ 「大義」が正解
- 「この改革には大儀名分がある」→ 「大義名分」が正解
-
日常会話での誤用
- 「最近、歩くのも大義になってきた」→ 「大儀」が正解
- 「殿様が家臣に『大義である』と言った」→ 「大儀である」が正解
-
ビジネスシーンでの誤用
- 「この新規事業には社会的な大儀がある」→ 「大義」が正解
- 「上司が部下に『大儀である』と言った」→ 時代劇では正しいが、現代では使われない
ビジネスシーンでは「大義」が使われることが多く、「大儀」はほとんど使われません。
そのため、「大儀」を誤って使わないように注意しましょう。
似た読み方の別の言葉との違い
「大義」と「大儀」以外にも、似た発音の言葉があるため、それらと混同しないようにしましょう。
| 言葉 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 大義(たいぎ) | 正義・道理・大きな目的 | 「国家の大義のために戦う」 |
| 大儀(たいぎ) | 面倒くさい・億劫・ねぎらい | 「歩くのも大儀になってきた」 |
| 怠惰(たいだ) | だらしなく怠けること | 「怠惰な生活を改めるべきだ」 |
| 大器(たいき) | 将来大物になる素質があること | 「彼は大器晩成型だ」 |
このように、同じような音を持つ言葉でも意味が異なるので、間違えないようにしましょう。
適切な場面での使い分け方
「大義」はこんな場面で使う!
✅ 政治や戦争:「国のための大義を掲げる」
✅ ビジネス:「このプロジェクトには大義があるのか?」
✅ 社会問題:「環境保護は大義のある活動だ」
「大儀」はこんな場面で使う!
✅ 日常生活:「最近、歩くのも大儀になってきた」
✅ 時代劇:「よく働いたな、大儀である!」
✅ 高齢者の会話:「何をするにも大儀じゃのう…」
このように、「大義」と「大儀」は使われる場面がまったく異なるため、誤用しないように意識するとよいでしょう。
まとめ:「大義」と「大儀」を間違えないためのポイント
- 「大義」は「正義や目的」、「大儀」は「面倒くさい・ねぎらい」
- 「大義」は政治やビジネスで使われるが、「大儀」は日常会話や時代劇で使われる
- 誤用しやすいケースに注意し、文章の文脈を確認する
- 「大義」と「大儀」以外の似た発音の言葉とも混同しないようにする
「大義」と「大儀」は、意味がまったく異なるため、適切な場面で正しく使い分けることが重要です。
特に、ビジネスシーンでは「大義」がよく使われる一方、「大儀」はほとんど使われないため、誤用しないよう注意しましょう!
まとめ:「大義」と「大儀」はこう使い分けよう!
ここまで、「大義」と「大儀」の意味や使い方の違いについて詳しく解説してきました。
最後に、それぞれのポイントを整理し、実生活でどのように使い分けるべきかをまとめます。
「大義」と「大儀」の意味をおさらい
まずは、それぞれの言葉の意味を簡単におさらいしましょう。
| 大義(たいぎ) | 大儀(たいぎ) | |
|---|---|---|
| 意味 | 正義、道理にかなった大きな目的 | 面倒くさい、億劫(古風な表現) |
| 使われる場面 | 政治、戦争、ビジネス、道徳 | 日常会話(特に年配者)、時代劇、歴史小説 |
| よく使われる表現 | 「大義名分」「大義を貫く」 | 「大儀である」「大儀そうな顔」 |
| 例文 | 「彼は国のための大義を掲げた」 | 「彼は歩くのも大儀になってきた」 |
使われる場面の違いを整理
それぞれの言葉が使われる場面を、具体的に整理してみましょう。
「大義」が使われる場面
✅ 政治・戦争:「国のために戦う大義があるのか?」
✅ ビジネス:「このプロジェクトには大義があるのか?」
✅ 社会活動:「環境問題に取り組むのは大義のある行動だ」
✅ 歴史・思想:「幕末の志士たちは、尊王攘夷という大義を掲げた」
「大義」は、社会的な正義や正当性が求められる場面で使われることが多いです。
特にビジネスや政治において、「大義名分が必要だ」といった表現が使われます。
「大儀」が使われる場面
✅ 日常会話(特に年配者):「年を取ると何をするのも大儀になってくる」
✅ 時代劇・歴史小説:「殿様が家臣に『大儀である』と言った」
✅ 疲れているとき:「今日は疲れているから、動くのも大儀だ」
「大儀」は、個人的な感情や身体的な負担を表現する言葉として使われます。
特に年配の人が「しんどい」「億劫だ」という意味で使うことが多いです。
また、時代劇や歴史小説では「大儀である」というねぎらいの言葉としても登場します。
「大義」と「大儀」の違いを簡単に覚えるコツ
「大義」と「大儀」を間違えずに使い分けるための簡単な覚え方を紹介します。
-
「義」は正義の「義」 → 大きな目的や使命を表す
- 例:「大義名分」「大義を貫く」
- ポイント:社会的な正当性があるかどうかを考える
-
「儀」は儀式の「儀」 → 動作や行動に関する言葉
- 例:「大儀である」「大儀そうな顔」
- ポイント:「面倒くさい」「疲れた」と言い換えられるかどうかを考える
また、「大儀(たいぎ)」の代わりに「億劫(おっくう)」という言葉を使うと、誤用を防ぎやすくなります。
たとえば、「最近、歩くのが大義になってきた」と言うと誤用になりますが、「最近、歩くのが億劫になってきた」と言い換えれば自然な表現になります。
文章やスピーチでの応用例
実際に「大義」と「大儀」を正しく使った例文をいくつか紹介します。
「大義」を使った例文
✅ 「この改革には大義があると信じています。」(政治・ビジネスの場面)
✅ 「人々のために働くことが、彼の大義だった。」(道徳的な意味)
✅ 「歴史上、多くの戦争が大義名分のもとで行われてきた。」(歴史的な文脈)
「大儀」を使った例文
✅ 「最近はちょっとした移動でも大儀になってきたな。」(日常会話)
✅ 「殿様が家臣に『大儀である』とねぎらった。」(時代劇のセリフ)
✅ 「長旅で疲れて、大儀そうな顔をしていた。」(動作の様子を表現)
このように、「大義」はスピーチやフォーマルな文章で使われることが多く、「大儀」はカジュアルな会話や古風な表現で使われることが多いです。
「大義」と「大儀」を正しく使いこなそう!
「大義」と「大儀」は、読み方は同じでも意味がまったく異なるため、正しく使い分けることが重要です。
最後に、ポイントを簡単にまとめます。
✅ 「大義」は、社会的な正義や使命を示す言葉
✅ 「大儀」は、面倒くさい・億劫を意味する古風な言葉
✅ 「大儀である」は、時代劇で使われるねぎらいの表現
✅ ビジネスやスピーチでは「大義」が使われ、日常会話では「大儀」が使われる
この違いをしっかり理解し、適切な場面で使い分けることで、より正確な日本語表現ができるようになります。
ぜひ、日常会話や文章作成に役立ててください!



















