
魚の成長過程には「仔魚(しぎょ)」「稚魚(ちぎょ)」「幼魚(ようぎょ)」という段階がありますが、それぞれの違いを説明できるでしょうか?
釣りや水産業、魚の生態を学ぶ上で、これらの用語の違いを理解することはとても重要です。
本記事では、「仔魚」「稚魚」「幼魚」の意味と違いを初心者向けにわかりやすく解説します。
また、成長ごとの特徴や水産業・釣りでの活用方法についても紹介するので、魚の生態に興味がある方はぜひ最後までご覧ください!
魚の成長過程と基本用語
魚の成長ステージはどう分類される?
魚は成長の過程でさまざまな段階を経て、大人(成魚)になります。
魚の種類によって多少の違いはありますが、一般的には以下のようなステージに分類されます。
| 成長段階 | 特徴 |
|---|---|
| 卵(らん) | 受精後の状態。殻や膜に包まれており、内部で発生が進む。多くの魚は水中に卵を産み、孵化までの期間を過ごす。 |
| 仔魚(しぎょ) | 孵化直後の状態。親魚とは異なる形態をしており、エサの捕食が未熟。卵黄を持つ種もある。 |
| 稚魚(ちぎょ) | ある程度成長し、親魚に近い形になりつつあるが、まだ未成熟。泳ぎが上達し、エサを積極的に捕るようになる。 |
| 幼魚(ようぎょ) | さらに成長し、形態はほぼ成魚に近いが、繁殖能力がない。群れで生活する魚も多い。 |
| 成魚(せいぎょ) | 繁殖が可能な状態。完全に成熟した個体。生態系の中で他の魚や動物と関わりを持ちながら生きる。 |
このように、魚の成長は段階ごとに大きく異なり、特に「仔魚」「稚魚」「幼魚」の違いは重要です。
「仔魚」「稚魚」「幼魚」の違いを簡単に説明
「仔魚」「稚魚」「幼魚」は、魚の成長段階を指す言葉ですが、それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
- 仔魚(しぎょ):孵化したばかりの魚で、体が小さく、親魚とは異なる形をしている。
泳ぎが未熟で、エサの捕食がうまくできないことが多い。
種類によっては、孵化直後に栄養を蓄えた「卵黄(らんおう)」を持っており、それを消費しながら成長する。 - 稚魚(ちぎょ):仔魚よりも成長し、親魚に似た形をし始めるが、まだ完全には発達していない。
泳ぎが上達し、エサを自力で捕食できるようになる。
成長の速度は種類によって異なり、環境や餌の量によって変わる。 - 幼魚(ようぎょ):さらに成長し、見た目は親魚とほとんど変わらないが、繁殖能力はまだない。
群れを作る種類も多く、外敵から身を守るための行動を学ぶ段階。
このように、「仔魚」「稚魚」「幼魚」は成長に伴って変化していきます。
仔魚とは?

仔魚の定義と特徴
「仔魚(しぎょ)」とは、魚が孵化した直後の段階を指します。
この時期の魚は非常に小さく、親魚とは異なる特徴を持っています。
仔魚の主な特徴
-
親魚と異なる形態:
- 多くの仔魚は体が透明で、まだ完全に発達していません。
- 背骨やヒレが未発達なため、泳ぐ能力が弱い。
-
卵黄(ヨークサック)を持つことが多い:
- 孵化直後の仔魚の中には、「卵黄(らんおう)」と呼ばれる栄養袋を持つものがいます。
- 卵黄を消費しながら成長し、ある程度成長すると外部のエサを食べ始めます。
-
外敵に対して無防備:
- 体が小さいため、他の魚や生き物のエサになりやすい。
- 生存率が低いため、自然界では非常に多くの卵が産まれる。
-
種類によって形状が異なる:
- 例えば、マグロの仔魚は糸のように細長く、ヒラメの仔魚は成魚とは全く異なる形をしています。
- 種類によっては、成魚になる過程で大きく姿を変えるものもある。
どんな魚に見られる?
仔魚の特徴は、魚の種類によって異なりますが、以下のような魚に見られます。
✅ 海水魚(例:マグロ、カツオ、ヒラメ、スズキなど)
✅ 淡水魚(例:メダカ、金魚、ナマズなど)
✅ 特殊な成長をする魚(例:ウナギは仔魚の時期に「レプトケファルス」と呼ばれる特殊な形態を持つ)
多くの魚は、仔魚の時期に成長しながら環境に適応していきます。
仔魚の代表例(魚種別の特徴)
代表的な魚の仔魚の特徴を見てみましょう。
| 魚の種類 | 仔魚の特徴 |
|---|---|
| マグロ | 仔魚の時期は非常に小さく、泳ぎが未熟。大量の卵を産むが、生き残るのは一部。 |
| ヒラメ | 仔魚の時期は体が左右対称だが、成長とともに片側の目が移動する。 |
| メダカ | 孵化直後の仔魚は透明で、小さなヒレを使って泳ぐ。 |
| ウナギ | 仔魚の時期は「レプトケファルス」と呼ばれ、葉っぱのような形をしている。 |
魚によって、仔魚の形や生態はさまざまです。
このように、「仔魚」は孵化したばかりで未発達な状態の魚を指します。次の段階は「稚魚」です。
稚魚とは?

稚魚の定義と特徴
「稚魚(ちぎょ)」とは、仔魚が成長し、親魚に近い形になりつつあるが、まだ未成熟な状態の魚を指します。
この段階では、泳ぎやエサの捕食能力が向上し、生存率が上がります。
稚魚の主な特徴
-
親魚に似た形をしている:
- 仔魚の時期とは異なり、魚種ごとの特徴が現れ始める。
- ただし、サイズはまだ小さく、成魚ほどの力はない。
-
エサを自力で捕食するようになる:
- 仔魚の頃は卵黄から栄養を取っていたが、稚魚になるとプランクトンや小さなエサを捕食する。
- この段階では、成長を促すためにたくさんのエサを食べることが重要。
-
泳ぎが上手くなる:
- ヒレが発達し、遊泳能力が向上する。
- まだ小さいため外敵には弱いが、逃げる能力が高くなる。
-
群れを作る種類が多い:
- 外敵から身を守るために、同じ成長段階の個体が集まることが多い。
- 例えば、イワシやアジの稚魚は「シラス」として知られ、大きな群れを作る。
どんな魚に見られる?
稚魚の段階は、ほとんどの魚に存在します。代表的な例を挙げると、
✅ 海水魚(例:アジ、イワシ、ブリ、マグロ、カツオ)
✅ 淡水魚(例:メダカ、コイ、ナマズ、ウグイ)
✅ 特殊な成長をする魚(例:ウナギは「シラスウナギ」として知られる)
特に海水魚の稚魚は、養殖の対象にもなりやすく、食用として流通することもあります。
稚魚の代表例(魚種別の特徴)
代表的な魚の稚魚の特徴を表でまとめます。
| 魚の種類 | 稚魚の特徴 |
|---|---|
| アジ・イワシ | 稚魚の時期は「シラス」と呼ばれ、大きな群れを作る。 |
| マグロ | 稚魚の段階で急速に成長し、大型魚へと育つ。 |
| メダカ | 稚魚になると親と似た姿になるが、体が小さくて弱い。 |
| ウナギ | 稚魚の段階では「シラスウナギ」と呼ばれ、透明な体をしている。 |
このように、稚魚はすでに親魚に似た形をしているものの、まだ未成熟であり、成長とともにさらに変化していきます。
この段階を経て、魚は次の「幼魚」のステージへと進みます。
幼魚とは?

幼魚の定義と特徴
「幼魚(ようぎょ)」とは、稚魚がさらに成長し、ほぼ成魚に近い姿になったが、まだ繁殖能力を持たない段階の魚を指します。
この段階では、親魚とほぼ同じ行動をとり、食性や生態も確立されていきます。
幼魚の主な特徴
-
見た目はほぼ親魚と同じ:
- 体のサイズが小さいものの、ヒレや体型などは親魚とほぼ同じ。
- 色や模様が成魚とは若干異なる場合もある(例:スズキの幼魚は黒い縞模様がある)。
-
単独行動や群れを作る習性が確立される:
- 稚魚の頃は群れで行動することが多いが、幼魚になると単独行動をとる魚も増える。
- 逆に、イワシやマグロのように成魚になっても群れを作る魚もいる。
-
エサの種類が増える:
- 小さなプランクトンだけでなく、小魚や甲殻類などを捕食する魚も出てくる。
- 例:スズキやブリの幼魚は、小型の魚やエビを捕食するようになる。
-
外敵への対策が発達する:
- 体が大きくなり、泳ぎがさらに上達する。
- 捕食者から逃げる技術を身につけたり、環境に適応した行動をとる。
どんな魚に見られる?
幼魚の段階は、多くの魚で見られます。
✅ 海水魚(例:スズキ、ブリ、カンパチ、マグロ)
✅ 淡水魚(例:コイ、フナ、ナマズ、アユ)
✅ 特殊な変態をする魚(例:ヒラメ、カレイは幼魚の段階で体が傾き、片側の目が移動する)
この時期の魚は釣りの対象にもなりやすく、「ワカナ(ブリの幼魚)」や「セイゴ(スズキの幼魚)」といった名前で呼ばれることもあります。
幼魚の代表例(魚種別の特徴)
代表的な魚の幼魚の特徴を表でまとめます。
| 魚の種類 | 幼魚の特徴 |
|---|---|
| スズキ | 幼魚の頃は「セイゴ」と呼ばれ、黒い縞模様がある。 |
| ブリ | 幼魚の頃は「ワカナ」「イナダ」と呼ばれ、成長に応じて名前が変わる。 |
| ヒラメ | 稚魚の頃は左右対称だが、幼魚になると片側の目が移動する。 |
| カンパチ | 幼魚の頃は「シオゴ」と呼ばれ、小型ながら泳ぎが速い。 |
幼魚の段階では、環境に適応しながら成長し、いよいよ成魚(大人の魚)へと向かいます。
「仔魚」「稚魚」「幼魚」の違いを比較!
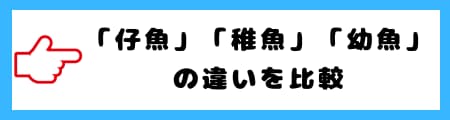
「仔魚」「稚魚」「幼魚」は、魚の成長過程における異なる段階ですが、それぞれの違いを明確に理解することで、魚の成長について深く知ることができます。
形態・生態の違い
| 成長段階 | 形態の特徴 | 主な生態 |
|---|---|---|
| 仔魚(しぎょ) | 孵化直後で、親魚とは異なる形。体が透明で、ヒレが未発達。 | 泳ぐ力が弱く、卵黄を栄養源とする場合が多い。自力での捕食が難しい。 |
| 稚魚(ちぎょ) | 体が親魚に近づくが、まだ未成熟。 | 自力でエサを捕食できるようになり、泳ぐ力も向上。群れを作る種類が多い。 |
| 幼魚(ようぎょ) | 見た目はほぼ成魚と同じだが、繁殖能力がない。 | 食性や行動が確立され、成長に必要なエサをたくさん食べる。単独行動を始める魚もいる。 |
このように、魚は成長段階ごとに形態や生態が大きく変化します。
釣りや水産業での使い分け
釣りや水産業では、成長段階ごとに異なる名称が使われることがあります。
✅ 釣りでの名称例
- スズキの幼魚は「セイゴ」、成長すると「フッコ」「スズキ」と呼ばれる。
- ブリの幼魚は「ワカシ」「イナダ」「ワラサ」など、成長に応じて名前が変わる。
✅ 水産業での活用例
- 稚魚の段階:養殖業では、稚魚を育てて成魚にすることが一般的(例:ウナギの「シラスウナギ」)。
- 幼魚の段階:市場では小型の魚が安価に取引されることが多い(例:ハマチ=ブリの若魚)。
まとめ:それぞれの段階を理解しよう
「仔魚」「稚魚」「幼魚」は、それぞれ成長段階ごとに特徴があり、生態や役割が異なります。
🔹 仔魚 → 孵化直後で、泳ぐ力が弱く、卵黄を栄養源にすることが多い
🔹 稚魚 → 自力でエサを捕食できるようになり、群れを作ることが多い
🔹 幼魚 → 見た目は成魚に近いが、繁殖能力がない
この知識を活かせば、魚の成長について深く理解することができ、釣りや水産業の知識としても役立ちます。
まとめ
「仔魚」「稚魚」「幼魚」の違いをおさらい
魚の成長過程は「仔魚」「稚魚」「幼魚」と段階的に進んでいき、それぞれの段階で形態や生態が大きく異なります。
| 成長段階 | 特徴 |
|---|---|
| 仔魚(しぎょ) | 孵化直後で親魚と異なる形をしており、泳ぐ力が弱い。エサを自力で食べることができず、卵黄を栄養源とすることが多い。 |
| 稚魚(ちぎょ) | 親魚に近い形になり、自力でエサを捕食できるようになる。泳ぐ能力が向上し、群れを作る種類も多い。 |
| 幼魚(ようぎょ) | 見た目は成魚に近くなるが、まだ繁殖能力がない。食性や行動が確立され、単独行動をとる種類も出てくる。 |
このように、魚の成長段階を知ることで、生態をより深く理解することができます。
釣りや観察に活かすポイント
🐟 釣りをする際のポイント
- 季節によって釣れる魚の成長段階が異なるため、「仔魚」「稚魚」「幼魚」の違いを知ることで釣りのターゲットを選びやすくなる。
- 幼魚は食用として流通することも多く、種類によっては「ワカシ(ブリの幼魚)」「セイゴ(スズキの幼魚)」のように市場で流通する名称が変わる。
🔍 水辺で魚を観察する際のポイント
- 小さな魚を見つけたら、それが「仔魚」「稚魚」「幼魚」のどの段階なのかを観察することで、成長のプロセスを学ぶことができる。
- 川や海で見られる魚のサイズや行動の違いを意識することで、生態系の仕組みが理解しやすくなる。



















