
「得手不得手」と「向き不向き」という言葉、似ているようで実は意味が違うことをご存じですか?
「プレゼンが不得手」と言うのと、「営業職に不向き」と言うのでは、伝わるニュアンスが変わります。
✅ 得手不得手 → 努力や経験によって克服できるスキルや技術のこと
✅ 向き不向き → その人の資質や性格により、適性があるかどうかを表す
この記事では、「得手不得手」と「向き不向き」の違いをわかりやすく解説し、日常生活や仕事での適切な使い分けを紹介します。
最後までご覧ください!
「得手不得手」とは
言葉の意味と読み方
「得手不得手(えてふえて)」とは、人が得意なこと(得手)と苦手なこと(不得手)を併せて表す言葉です。
「得手」は「えて」、「不得手」は「ふえて」と読みます。
この言葉は、個人の能力やスキルに関する場面で使われることが多く、「〇〇が得手」「〇〇は不得手」といった形で用いられます。
例えば、スポーツや勉強、仕事のスキルなど、何かの技術的な習熟度を示す際に使われることが一般的です。
✅ 「得手」 → 得意なこと、上手にできること、精通していること
✅ 「不得手」 → 苦手なこと、うまくできないこと、慣れていないこと
たとえば、以下のように使われます。
- 彼は数学が得手だが、国語は不得手だ。
- プレゼンは得手ではないが、資料作成は得手だ。
- 料理が不得手な人でも、簡単なレシピなら挑戦できる。
このように、「得手不得手」は、特定の分野やスキルに関しての能力の差を表現する言葉であり、「好き嫌い」とは異なる点が特徴です。
好きでも不得手なことはありますし、得手でも好きとは限らないこともあります。
由来と語源
「得手不得手」という言葉の由来は、日本語の古語や漢語の影響を受けています。
「得手」の由来
「得手(えて)」は、「得る(える)」という動詞と、「手(て)」という名詞が組み合わさった言葉です。
- 「得る」 = 手に入れる、習得する
- 「手」 = 技術や能力
つまり、「得手」は「自分のものにした技術・能力」という意味になります。
古くから「手際の良さ」や「巧みさ」を指す言葉として使われてきました。
「不得手」の由来
「不得手(ふえて)」は、「得手」に「不(ふ)」をつけた言葉です。
「不得(ふとく)」という言葉もあり、これは「得ることができない」という意味を持ちます。
そのため、「不得手」は「技術を習得しておらず、うまくできないこと」を指すようになりました。
歴史的な使用例
平安時代の文献や江戸時代の書物にも「得手」や「不得手」という表現が見られ、武芸や芸事の習熟度を語る際によく使われました。
例えば、剣術や書道などの分野で「得手な技」「不得手な作法」といった形で用いられています。
現代では、スポーツや勉強、仕事のスキルを表す際に使われることが多く、「得手不得手があるのは当たり前」といった表現で、多様な個性を尊重する意味でも使われることがあります。
使い方と例文
「得手不得手」は、主に個人の能力やスキルに関する話題で使われます。
得意・不得意を表現する際に便利な言葉ですが、状況に応じて適切に使うことが重要です。
1. 基本的な使い方
✅ 「〇〇が得手 / 不得手だ」 → 特定の分野やスキルに関する得意・不得意を表す
✅ 「得手不得手がある」 → 人には得意なことと苦手なことがある、という一般論を示す
2. 例文(会話や文章での使い方)
📌 日常会話での使用例
- 私は絵を描くのが得手だけど、歌うのは不得手だ。
- 料理は不得手だけど、練習すれば上手くなるかな?
- 彼はスポーツ全般が得手だが、勉強は不得手らしい。
📌 ビジネスシーンでの使用例
- 彼女は企画の立案は得手だが、細かい事務作業は不得手のようだ。
- チームのメンバーそれぞれに得手不得手があるので、役割分担を考えよう。
- 人には得手不得手があるから、苦手なことは得意な人に任せるのが効率的だ。
📌 学習や自己成長の場面での使用例
- 語学の学習は人によって得手不得手があるので、無理のない方法で学ぶことが大切だ。
- どんな仕事にも得手不得手があるが、不得手な分野でも努力次第で克服できることもある。
- 得手不得手を理解した上で、自分に合ったキャリアを考えよう。
3. 注意点(誤用しやすいポイント)
❌ 「好き嫌い」とは違う
「得手不得手」は能力やスキルに関する話であり、「好き嫌い」とは異なります。
例)
- 誤:「カレーは不得手です。」(※食べ物の好き嫌いには使わない)
- 正:「辛いものを食べるのが不得手です。」(※食べる行為のスキルとしてならOK)
「向き不向き」とは
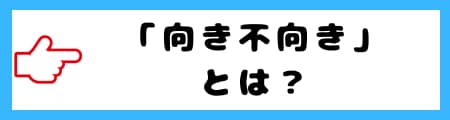
言葉の意味と読み方
「向き不向き(むきふむき)」とは、物事に対する適性や適合性を表す言葉です。
「得手不得手」が現在の能力や習熟度を表すのに対し、「向き不向き」はその人の性格や資質が、その物事に適しているかどうかを指します。
✅ 「向き」 → その人に合っている、適性がある
✅ 「不向き」 → その人に合っていない、適性がない
この言葉は、職業や性格、人間関係、作業のスタイルなど、スキルというよりも「向いているかどうか」を表す際に使われるのが特徴です。
例えば、以下のように使われます。
- 彼は細かい作業が苦手なので、事務仕事は不向きかもしれない。
- 明るく社交的な性格なので、接客業に向いている。
- コツコツと努力できる人は、研究職に向いていると言われる。
「向き不向き」は、努力では変えにくい「資質や特性」に焦点を当てている点が、「得手不得手」との大きな違いです。
使い方と例文
「向き不向き」は、物事に対する適性や特性を示すときに使われます。
努力や経験で変わる「得手不得手」とは異なり、「その人の本質的な向き・不向き」に関する話題で使われることが多いです。
1. 基本的な使い方
✅ 「〇〇に向いている / 向いていない」 → 適性がある・ないを表す
✅ 「〇〇は向き不向きがある」 → 物事によって適性が分かれることを示す
2. 例文(会話や文章での使い方)
📌 日常会話での使用例
- 彼は人と話すのが好きだから、営業の仕事に向いていると思う。
- 細かい作業が苦手なので、裁縫は不向きかもしれない。
- どんな仕事にも向き不向きがあるから、自分に合ったものを選びたい。
📌 ビジネスシーンでの使用例
- 彼はリーダーシップがあるので、管理職に向いているだろう。
- ルールに縛られるのが苦手な人は、公務員の仕事には不向きかもしれない。
- 新しいことにチャレンジするのが好きな人は、スタートアップ企業に向いている。
📌 学習や自己成長の場面での使用例
- 勉強には向き不向きがあるが、不得意な教科でも工夫すれば克服できる。
- クリエイティブな仕事が向いている人は、デザインや執筆などの分野で活躍しやすい。
- 適性を考えると、専門職よりもマルチな業務ができる職種の方が向いているのかもしれない。
3. 注意点(誤用しやすいポイント)
❌ 「向き不向き」と「好き嫌い」は別物
向き不向きは、その人の適性を示すものであり、好き嫌いとは違います。
例)
- 誤:「私は運動が嫌いだから、スポーツは不向きです。」
- 正:「私は持久力がないので、長距離走は不向きです。」
「得手不得手」と「向き不向き」の違い
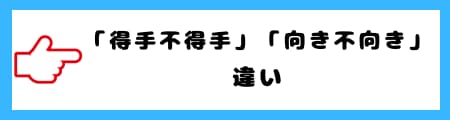
「得手不得手」と「向き不向き」はどちらも「できる・できない」を表す言葉ですが、意味や使われる場面が異なります。
この違いを理解することで、適切な場面で使い分けることができます。
意味の違い
「得手不得手」と「向き不向き」の違いを明確にするために、以下のポイントに注目しましょう。
| 得手不得手(えてふえて) | 向き不向き(むきふむき) | |
|---|---|---|
| 意味 | ある物事に対する習熟度や技術の有無を示す | 物事への適性や性格的な向き・不向きを示す |
| 主な対象 | スキル・経験・技術(努力で習得可能) | 資質・性格・特性(努力では変えにくい) |
| 変えられるか? | 練習や努力で克服できる場合が多い | もともとの資質によるため、変えにくい |
| 使い方の例 | 「ピアノが得手 / 不得手」 「プレゼンは不得手だが、資料作成は得手だ」 |
「細かい作業が得意でも、事務仕事に向いているとは限らない」 「人と話すのが好きなら、接客業に向いている」 |
たとえば、「ピアノを弾くのが得手」という場合、それは過去の練習や経験によって得意になったことを意味します。
しかし、「音楽の仕事に向いているかどうか」は、単にピアノが弾けるだけでなく、表現力や感性、継続的な努力ができるかどうかといった資質にも関わります。
使い分けのポイント
✅ 「努力で克服できるかどうか」で考える
- 得手不得手 → 練習すれば上達できるもの(例:スポーツ、勉強、プレゼン)
- 向き不向き → もともとの性格や適性に関わるもの(例:接客、研究、管理職)
✅ 場面ごとの使い分け
| 場面 | 得手不得手 | 向き不向き |
|---|---|---|
| 仕事 | 「エクセル作業が得手 / 不得手」 | 「細かいデータ管理の仕事は不向き」 |
| スポーツ | 「水泳が得手 / 不得手」 | 「個人競技よりもチームスポーツが向いている」 |
| 勉強 | 「数学が得手 / 不得手」 | 「暗記よりも論理的思考を活かす学問が向いている」 |
✅ 組み合わせて使うことも可能
- 例1: 彼は計算が不得手だが、根気強く取り組むので経理の仕事に向いている。
- 例2: デザインの仕事は得手だが、自由な発想を求められる環境には不向きかもしれない。
たとえば、計算が不得手でも、努力と経験を積めばある程度のスキルは身につきます。
しかし、計算に強い人が必ずしも経理の仕事に向いているとは限らず、集中力や正確性、慎重さなどの資質が求められます。
このように、「得手不得手」と「向き不向き」は重なる部分もありますが、焦点が違うことが分かります。
注意すべき誤用例
「得手不得手」と「向き不向き」を混同すると、意味が伝わりにくくなることがあります。
以下のような誤用に注意しましょう。
誤用例1:「不得手」と「不向き」の混同
❌ 「私は人と話すのが不得手だから、営業職は不得手です。」
✅ 「私は人と話すのが不得手だから、営業職には不向きかもしれません。」
→「不得手」は単にスキルの問題であり、努力次第で改善できます。
しかし、「営業職に不向き」は、性格や適性が合わないことを指します。
誤用例2:「向き不向き」と「好き嫌い」の混同
❌ 「私は運動が嫌いだから、スポーツは不向きです。」
✅ 「私は持久力がないので、長距離走は不向きです。」
→「向き不向き」は適性の問題であり、単なる「好き・嫌い」とは異なります。
運動が嫌いでも、持久力があるなら長距離走に向いている可能性があります。
誤用例3:「不得手なのに向いている」ケース
❌ 「彼はピアノが不得手だから、音楽の道には不向きだ。」
✅ 「彼はピアノが不得手だが、作曲のセンスがあるので音楽の仕事に向いている。」
→不得手なことがあっても、全体としてその分野に向いている場合もあります。
ピアノは不得手でも、作曲や音楽理論に優れていれば、音楽の道に進むことは可能です。
まとめ:両者の違いを正しく理解しよう
🔹 得手不得手はスキルや経験によるもの → 努力次第で変えられることが多い
🔹 向き不向きは資質や性格によるもの → 努力しても変えにくいことがある
🔹 「好き嫌い」とは別物 → 「不得手=嫌い」ではなく、「不向き=嫌い」でもない
「得手不得手」と「向き不向き」を正しく使い分けることで、自分の強みを活かし、適した道を選ぶ助けになります。
日常生活や仕事でも、これらの概念を意識することで、自分に合った環境を見つけることができるでしょう。
具体的な使用例
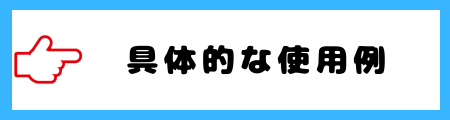
「得手不得手」と「向き不向き」は、日常生活やビジネスの場面でどのように使われるのでしょうか?
実際の会話や文章での使用例を見ていきましょう。
日常会話での使用例
日常生活の中で、「得手不得手」と「向き不向き」は以下のように使われます。
📌 家族や友人との会話
- 「お兄ちゃんは料理が得手だけど、掃除は不得手だよね。」
- 「私は運動が不得手だから、一緒にスポーツをするのは気が引けるな。」
- 「細かい作業が向いていないけど、体を動かす仕事は向いているかも。」
📌 趣味・学習に関する話題
- 「英語は不得手だけど、歴史の勉強は得手だから、楽しい!」
- 「絵を描くのが得手なら、デザインの仕事にも向いているかもしれないよ。」
- 「プログラミングは向いているかどうかわからないけど、挑戦してみたいな。」
ビジネスシーンでの使用例
職場や仕事の中でも、「得手不得手」と「向き不向き」は適切に使い分ける必要があります。
📌 職場での会話
- 「プレゼンは不得手ですが、資料作成は得手なのでサポートできます。」
- 「〇〇さんは交渉が得手だから、クライアント対応をお願いしたい。」
- 「私は計画を立てるのが不得手だから、チームで補い合えたらいいですね。」
📌 仕事の適性について
- 「彼はリーダーシップがあるので、管理職に向いていると思う。」
- 「細かい作業が不得手でも、創造力があるならマーケティングの仕事に向いているかも。」
- 「自由な発想を求められる仕事は、ルールに厳格な人には不向きなことが多い。」
学習や自己啓発での活用方法
「得手不得手」と「向き不向き」を理解すると、学習やキャリアの選択に役立ちます。
📌 学習のコツ
- 不得手な科目の勉強方法を工夫する
- 例:「数学が不得手なら、問題をたくさん解いて慣れるのが大事。」
- 向いている学習方法を見つける
- 例:「暗記が不得手なら、図や表を使って理解する方法が向いている。」
📌 キャリア選びの考え方
- 得手不得手よりも「向き不向き」を重視する
- 例:「事務作業が得手でも、単調な仕事が苦手ならオペレーター業務は不向きかもしれない。」
- 向いている仕事を選ぶことで、長く続けられる
- 例:「営業が不得手でも、人と関わる仕事が向いているなら接客業のほうが合うかもしれない。」
まとめ
- 「得手不得手」はスキル、「向き不向き」は適性を表す
- 日常会話や仕事で適切に使い分けることで、より的確な表現ができる
- 自己分析やキャリア選択にも役立つので、自分に合った選択をする際のヒントになる
まとめ
この記事では、「得手不得手」と「向き不向き」の違いについて詳しく解説しました。
それぞれの言葉の意味や使い方を振り返ってみましょう。
両者の違いの要点整理
| 得手不得手(えてふえて) | 向き不向き(むきふむき) | |
|---|---|---|
| 意味 | 習熟度や技術の有無を示す | 物事への適性や向いているかどうかを示す |
| 主な対象 | スキル・経験・技術 | 資質・性格・特性 |
| 変えられるか? | 努力や練習で克服できることが多い | 本質的な特性なので変えにくい |
| 使い方の例 | 「ピアノが得手 / 不得手」 「プレゼンは不得手だが、資料作成は得手だ」 |
「細かい作業が得意でも、事務仕事に向いているとは限らない」 「人と話すのが好きなら、接客業に向いている」 |
✅ ポイント:努力で克服できるのが「得手不得手」、本質的な適性を表すのが「向き不向き」
適切な使い分けの重要性
「得手不得手」と「向き不向き」を適切に使い分けることで、自分の強みや課題を正しく理解し、適切な判断を下すことができます。
📌 学習・仕事の場面で役立つ考え方
- 得手不得手を知ることで、努力すべき分野が見える
- 例:「プレゼンが不得手なら、話し方を練習することで改善できる」
- 向き不向きを理解すると、無理なく能力を発揮できる環境を選べる
- 例:「細かい作業が不得手でも、コミュニケーション能力が高いなら営業職に向いているかもしれない」
得手不得手は改善できるもの、向き不向きは自分に合った環境を選ぶための指標として活用しましょう。
今後の学習へのアドバイス
1. 自分の「得手不得手」と「向き不向き」を知る
- どんなことが得意で、どんなことが苦手かリストアップしてみる
- 自分の資質や性格がどの分野に向いているのか考えてみる
2. 「不得手」なことをどう克服するか考える
- 具体的にどんな努力をすれば改善できるのかを考える
- 無理に克服するのではなく、得意な人と協力することも選択肢
3. 「不向き」なことに無理に挑戦しすぎない
- 無理に向いていないことを続けるとストレスが溜まりやすい
- 自分に合った環境や役割を見つけることが大切
最後に
「得手不得手」と「向き不向き」を理解することで、自分の適性を知り、より充実した人生を送るためのヒントを得ることができます。
✅ 得手不得手は努力で克服できるスキルや技術の問題
✅ 向き不向きは、努力では変えにくい資質や適性の問題
✅ 自分の特性を理解し、適切な選択をすることが大切
これらの違いを意識しながら、今後の学習や仕事、キャリア選択に活かしてみてください。



















